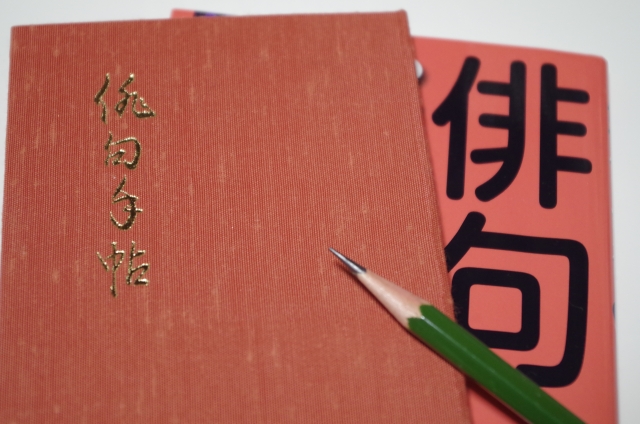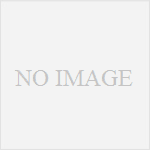概要
H011124 共有物の持ち分
相続人なくして共有者の一人が死亡したが、特別縁故者がいる場合には、まず共有持ち分が( )に対する財産分与の対象となり((958条の3))、財産分与がなされず共有持ち分を承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、( )に帰属する。
《詳細》
相続人なくして共有者の一人が死亡したが、特別縁故者がいる場合には、まず共有持ち分が特別縁故者に対する財産分与の対象となり((958条の3))、財産分与がなされず共有持ち分を承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、255条により他の共有者に帰属する。
《詳細を隠す》
第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)((昭和37年の改正により新設された規定))
特別縁故者の定義
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
- 具体的には該当する者の例
- 内縁の妻(配偶者)
- 事実上の養子
- 特別縁故者がいない場合、または特別縁故者として認められなかった場合
- 相続財産は国庫に帰属する。
- 遺産(相続財産)に共有持分が含まれる場合
- 共有持分も「清算後残存すべき相続財産」に含まれるとし、民法第958条の3が優先される((最高裁平成元年11月24日民集43巻10号1220頁))
第952条(相続財産の管理人の選任)
- 前条の場合には、家庭裁判所は、( )の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
《詳細》
利害関係人又は検察官《詳細を隠す》
- 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
- 第952条2項の公告があった後( )以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、( )を下ることができない。
《詳細》
2箇月《詳細を隠す》
- 第927条2項 から第四項 まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
第958条(相続人の捜索の公告)
前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、( )によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を( )しなければならない。この場合において、その期間は、( )を下ることができない。
《詳細》
前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。
《詳細を隠す》
H081031 裁判による分割
分割の方法は、258条2項の規定にかかわらず、( )も含まれる。
《詳細》
全面的な価値賠償
《詳細を隠す》
-
第258条(裁判による共有物の分割)
- 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を( )ことができる。
《詳細》
裁判所に請求する《詳細を隠す》
- 前項の場合において、共有物の現物を( )とき、又は( )ときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
《詳細》
前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。《詳細を隠す》
価格賠償
民法には規定が存在しない方法で、どちらか一方の単有とし、他方に金銭などの財産的補償をすること。
部分的価格賠償(S620422)
現物分割をした現物の価格に過不足が生じたときは、持分の価格以上に現物を取得する者に超過分の対価を支払わせて過不足の調整をすることができる。
全面的価格賠償(H081031)
- 共有物の性質及び形状・共有者の数及び割合・共有物の利用状況などを総合的に考慮し、全面的価格賠償が相当であると認められ、
- 共有物の価格が適正に評価され、
- 当該共有物を取得する者に支払能力があり、
- 他の共有者にその持分の価格を取得させることが共有者間の( )を( )ときに許される。
《詳細》
- 他の共有者にその持分の価格を取得させることが共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が存在するときに許される。
《詳細を隠す》